覚醒剤取締法違反の刑事事件で、控訴審の国選弁護人となり活動しています。
覚醒剤取締法違反の検挙人員の推移は、近年おおむね横ばいから減少傾向であり、令和元年には8730人と、昭和50年以来、44年ぶりに1万人を下回りました。
他方、覚醒剤取締法違反の成人検挙人員のうち、同一罪名再犯者率(同法違反の成人検挙人員に占める同一罪名再犯者の人員の比率)は、近年上昇傾向にあり、令和元年は、66.9%となりました(令和2年版犯罪白書)。
薬物への依存から、多くのケースで再犯にいたり、抜け出せなくなっていることがうかがわれます。
刑事司法における薬物事犯の処遇は、同種前科・前歴によって量刑の相場がおおむね決まっているといわれます。行為責任主義の観点から、量刑は、行為・結果・動機から量刑の大枠が決まるといわれますが、薬物事犯においては薬物の使用方法という行為類型にあまり大きな意味はなく、自己使用の場合は被害者もいないため結果も重視されません。そのため、裁判官も同種前科・前歴をみて、おおむね過去の量刑傾向にしたがって刑を決めることが多く、量刑不当となるケースは多くありません。
また、民事裁判とは異なり、刑事裁判における控訴審は、事後審といわれ、事件の審理をやり直すのではなく、第1審判決の当否を事後的に審査することが主になります。第1審の裁判官の判断が間違っていた、不合理だったといえなければならず、破棄判決のハードルは高くなります。実際に、令和元年度の覚醒剤取締法違反について被告人側からの控訴申立件数は1220件ありましたが、第1審判決が破棄されたのはわずか47件でした(令和元年度司法統計)。
さて、担当することとなった事件は、量刑不当を理由とする被告人本人による控訴事件。上述のような厳しい見通しを伝えつつ、「やれるだけやってみましょう」と8ページにわたる控訴趣意書を書き上げました。控訴趣意書とともに、薬物依存症の民間リハビリテーション施設であるダルクの連絡先一覧などが記載された書籍を被告人本人に差入れ。後日、被告人から「一生懸命やって下さった事は十分伝わってきました。」「社会復帰後、自分が薬物依存症である事をしっかり認識し、しっかり生き直していきます。」とお手紙をいただきました。
判決をとることだけが弁護人の役割ではないと実感しました。被告人が更生して薬物依存と向き合い、自分の人生を生き直してくれることを願ってやみません。
富永
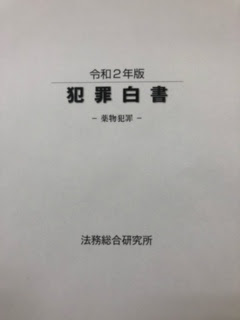
0 件のコメント:
コメントを投稿