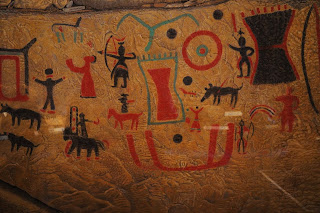先日、家計相談支援事業@生活困窮者自立支援法について書いた。
http://blog.chikushi-lo.jp/2025/02/blog-post_14.html
きょうは日常生活自立支援事業及び暮らしのサポートセンター事業について書こう。
日常生活自立支援事業は、認知機能が十分でない認知症高齢者や知的障害者、精神障害者を対象とした権利擁護のための制度である。
われわれ弁護士にとって馴染みのあるのは、成年後見制度である。やはり認知症、知的障害、精神障害などにより物事を判断する能力が十分でない人について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度である。援助者は、本人の判断能力が少ない順に、後見人、補佐人、補助人となっている。
成年後見が民法に基づくのに対し、日常生活自立支援事業は社会福祉法に基づく制度である。前者を運営するのは家庭裁判所であり、後者を運営するのは福岡県社会福祉協議会である。
前者の支援内容は、別の機会に書こう。後者の支援内容は、福祉サービスの利用援助や苦情解決制度の利用援助、住宅改造、居住家屋の賃借、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続に関する援助など。具体的には預金の払い戻しや解約などの金銭管理、定期訪問などにより生活変化を察知することなどである。
本事業の利用は契約による。そのため、本事業の対象者は、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分でありながら、かつ、本事業の契約内容が判断できるレベルの能力は維持している必要がある。
筑紫野市の社会福祉協議会は、福岡県から委託を受けて、本事業を実施している。筑紫野市社協は、同事業だけでなく、暮らしのサポートセンターを設置し、独自事業として暮らしのサポートセンター事業を実施している。生活保護を受給している人は前者を、そうでない人は後者を利用していただいている。
暮らしのサポートセンターは運営審議会を設け、運営に関する事項について審議している。当職はその審議会の委員長をおおせつかっている。
たとえば、自宅で独居生活をしているものの、高齢化がすすみ支払いの滞納や二重払いが見られるようになった高齢者について、手続き代行サービス・財産保全サービスを契約する。具体的な支援の内容は毎月2回の訪問(生活費の払戻等)、通帳・はんこ等の預りである。
成年後見が必要になった高齢者宅を訪問すると、日常生活が維持できず、財産管理が悲惨な状況になっていることがある。このサービスを受けることができれば心強い。配偶者や子どもがなく、東京や大阪で姪がひとり心配しているなどというケースなどではうってつけな制度である。
費用もビックリするくらい低廉である。自分も判断力が怪しくなってきたら、社協にお世話になろうと思う。