NHK「ダーウィンが来た!」だったか、「ワイルドライフ」だったか、「サイエンスZERO」だったか、そのいくつかだったか。鈴木俊貴さんがシジュウカラ語を解する番組をみたことはあった。
『僕には鳥の言葉がわかる』がヒットし、本屋に平積みになっていることも知っていた。でもそれを買うところまでは至っていなかった。
https://www.nhk.jp/p/zero/ts/XK5VKV7V98/blog/bl/pMLm0K1wPz/bp/pJ68O13Oyn/
今般、例の鈴木保奈美の「あの本、読みました?」(BSテレ東)に作者が出演し、いろいろと熱く語るのをみて、同書を買ってしまった。
https://www.bs-tvtokyo.co.jp/anohon/
同番組をみながら、教科書がなぜ面白くないのかに思いをいたした。知識偏重、紙数の制約から、もろもろの研究成果の上澄みだけ、学会の通説的見解の結論だけを紹介しているためだから。
見解の相違が生じた原因、研究者たちの探求、自説を裏付ける証拠の発見、それが通説へと収斂していった経過などを紹介すれば、とても面白いものになるのだろうけれど。
鈴木博士の研究も、「ダーウィンが来た!」だったか、「ワイルドライフ」だったかでみたときは、シジュウカラもただ鳴いているだけではなく、コミュニケーションをしている!というトリビア的なネタとして紹介されていたと思う。
鈴木保奈美の番組を面白くかんじたのは、当初、そのような仮説を思いついてから、同説を実証するまでの涙ぐましい努力が語られていたから。そこを面白いと思い、同書を購読するに至ったのである。
高校生のころ双眼鏡を入手し、バードウォッチングにはまる。図書館に通い詰め、コンラート・ローレンツの『ソロモンの指輪』などを読みあさる。大学で鳥の研究者を目指す。
『ソロモンの指輪』などは、わが大学の生協でも指定図書として平積みになっていた。残念ながら、そちらの方面へ向かうことにはならなかった。19の夏。
鈴木さんが大学三年のとき、中軽井沢で出会ったのが、シジュウカラ、コガラ、ヤマガラ、ヒガラ、ゴジュウカラ(以上〝カラ類”)のほか、コゲラ、アカゲラ、アオゲラ(以上〝キツツキ類”)からなる混群である。
ある日、コガラが「ディーディーディー」と鳴いていた。なんだろう?と思っていると、シジュウカラやヤマガラたちがその鳴き声のほうへと飛んでいった。鳴き声のほうへ行くと、誰かがヒマワリのタネをまいていた。コガラはそれを他の個体に知らせていたのだった。種をこえて。
実はこれは出発点となる仮説で、これを実証するためには涙ぐましい努力が必要となる。個体差なども考慮すると、10羽のシジュウカラにコガラの「ディーディーディー」を聞かせ、他の10羽には別の鳴き声を聞かせて、いつも同じ結果がでなければ偶然の要素を排除できない。
面白いのはこれが混群のなかで起こっているということだ。混群とは違う種の鳥が群れをなしているということ。コガラとコゲラ、呼び方は似ているけれども、種が違う。一方はスズメの仲間で、他方はキツツキの仲間だ。
利己的な遺伝子の考えからすれば、コガラが自分のエサを減らして、他の種にエサのありかを教えることは考えられない。しかし、混群のなかではそれが行われている。
なぜか。そのほうがエサは減るけれども、猛禽類など敵に襲われる危険が減るから。自分だちだけで生活しているときは、しょっちゅう上空を警戒していなければならない。エサ探しに集中できない。種を超えて、猛禽類接近の危険を伝え合うようになれば、上空を警戒する時間が減り、エサ探しに集中できるというわけだ。なるほど。
なんだか。EU統合の話に似ている。人類も宇宙人侵略の危機に直面しないと仲よくできないのだろうか。それとも小柄なコガラたちに学ぶことができるのだろうか。シジュウカラというけれど、もうとっくに40歳は過ぎちゃったんだけど。
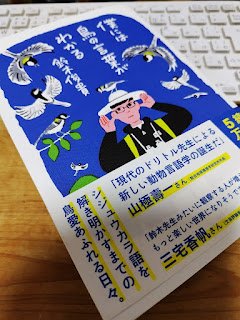
0 件のコメント:
コメントを投稿